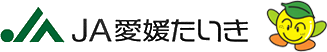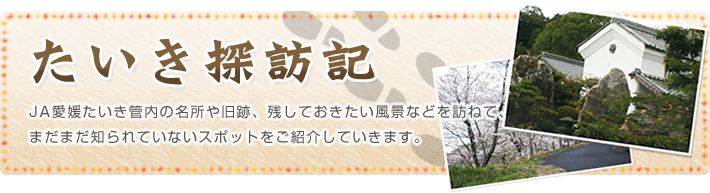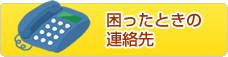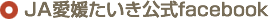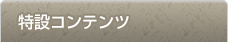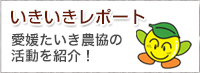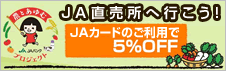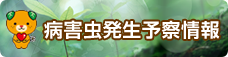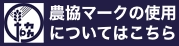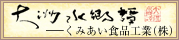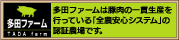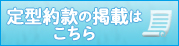高昌寺を訪ねて
内子町にある、とても大きな涅槃仏の安置されている高昌寺。室町時代、嘉吉元年(1441年)に防州泰雲寺の覚隠禅師門下の十哲であった大功円忠大和尚が、現在の内子町松尾地区に、寺院を創建し、浄久寺と称したのが高昌寺の起源です。
平成10年11月1日に安置された高昌寺の石造涅槃仏は、長さ10m、高さ3m、重さは約200tあります。涅槃仏は釈迦が入滅する様子を仏像として表したものです。ほとんどの場合、右手を頭の下にしくか、右手で頭をささえるようにして横になった姿をしています。18世慈舟台漸和尚によって創始された「涅槃まつり」は200年の歴史をもっており、毎年3月15日に行われています。本堂では地獄極楽絵図を観賞できたり、よもぎ餅が振舞われたりと、多くの人が訪れ賑わうそうです。
高昌寺には孝子桜と呼ばれる桜の木があります。松山の山越えの里で、桜の花が大好きな老人が病に倒れ、死ぬ前に桜が見たいというのを聞いた息子が一心不乱に祈ったところ、次の日見事な桜の花が咲いたそうです。これによって病気の父親を慰めたことから、孝子桜と呼ばれました。高昌寺の桜はこの木を分植したものだそうです。松山龍隠寺の親木は松山空襲により枯死してしまったため、今はこの木が残るのみです。

高昌寺

石造涅槃仏